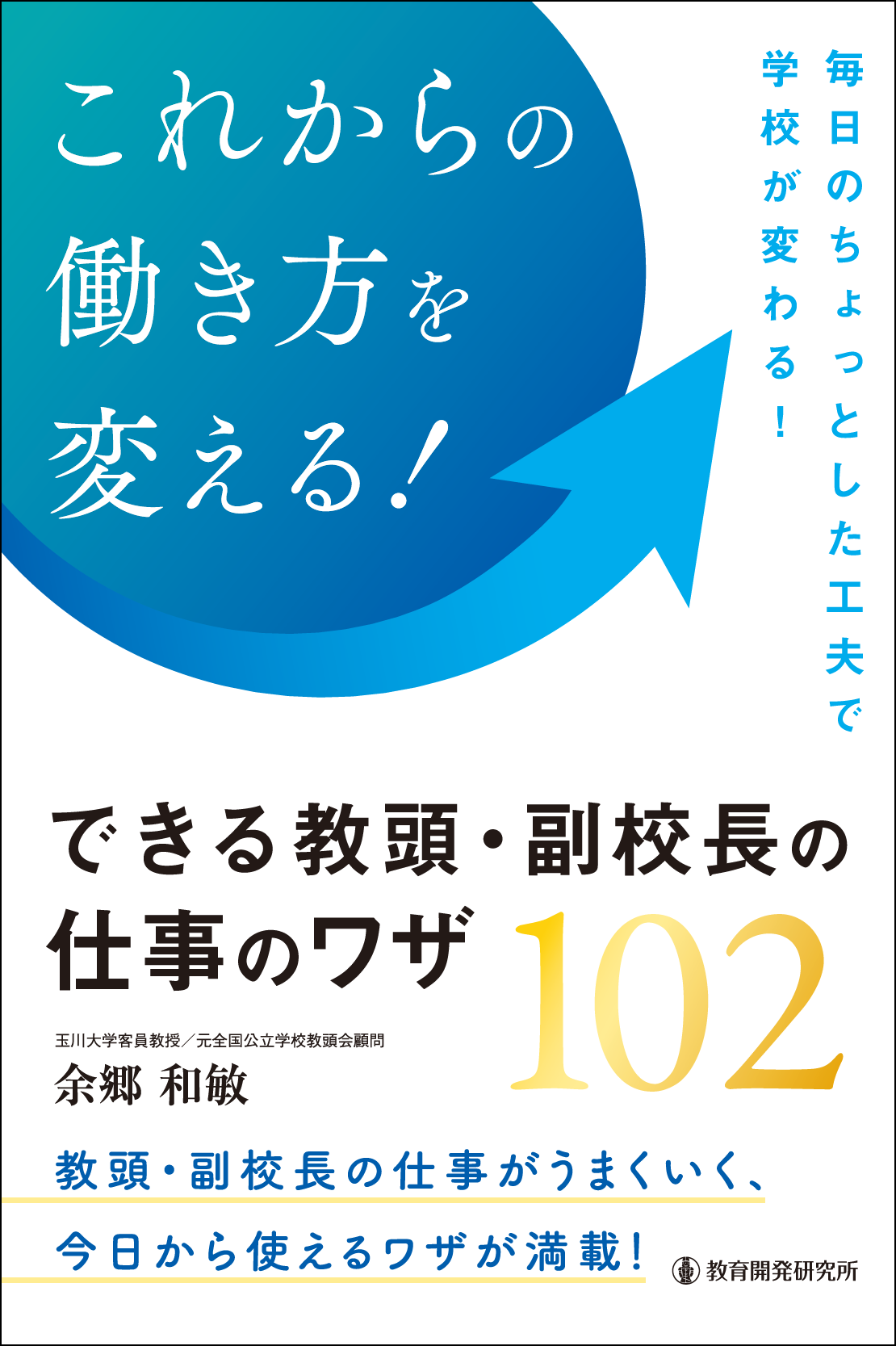これからの働き方を変える!できる教頭・副校長の仕事のワザ102
[本書の概要]
教頭・副校長の仕事がうまくいく、今日から使えるワザが満載!
教育現場が大きく変わる今、学校運営の要である教頭・副校長に求められる役割もまた、変化してきています。
教員の専門性を支え、よりよい学校づくりを目指すために今日からできることを、「学校を支える」「学校を動かす」「学校を改善する」「働き方を変える」「教員を育てる」「子ども・保護者・地域と関わる」の6つの視点から解説します。
「学校運営」のスペシャリストである教頭・副校長が、忙しい毎日を乗り越え、よりよい学校運営を実現するためのヒントが詰まった1冊です。
[著者] 余郷和敏
[刊行日] 2025-04-22 [形態] 書籍
[定価] 2420 円(税込) [判型] 四六判 [頁数] 192頁
[ISBN] 978-4-86560-607-2
[本書の目次]
はじめに
1章 学校を支える
1 校長との連携を深める
1-1 学校経営方針の実現を図る
1-2 教頭・副校長としての経営方針を立てる
1-3 積極的に提案をしていく
1-4 ToDoを文字化する
2 情報を収集し、対策を立て、発信する
1-5 相手に笑顔で接し、いろいろな声かけをする
1-6 情報収集の道筋をつくっておく
1-7 定例で打ち合わせを行うとともに、いつでも相談を受ける
1-8 巡回では七つ道具を必携する
3 校長と教職員の間をつなぐ
1-9 指示・助言は具体的に行う
1-10 不平不満を業務改善につなげる
4 安全管理を徹底する
1-11 さまざまな状況を想定する
1-12 複数による確認を徹底し、チェックリストを整備する
1-13 最後は自分で確認する
5 校長をめざす
1-14 二の矢、三の矢を想定する
1-15 自分の考えに基づく具申を考えておく
2章 学校を動かす
1 教職員同士の関係を活性化させる
2-1 毅然とした態度で接する
2-2 少人数での協議の場を設ける
2-3 みんなの前で褒め、指導は個別で行う
2-4 仕事の進め方をつかむ
2 教職員から問題点を引き出す
2-5 教員の状況を把握する
2-6 教員以外の職員から情報を引き出す
2-7 組織を活用する
3 校内でのチームをつくる
2-8 教育課程を管理するチームをつくる
2-9 予算の適正な執行を確認するチームをつくる
4 次年度の計画を立てる
2-10 実施時期を考える
2-11 目的をはっきりさせる
2-12 各種の情報提供をする
5 1年間を総括する
2-13 学校教育の管理――教育課程を振り返る
2-14 所属職員の管理――成長・成果を評価する
2-15 学校施設の管理――次年度につなげる点検・改善計画を立てる
2-16 学校事務の管理――予算執行を振り返る
6 教育委員会との連携を図る
2-17 部署による違いに対応する
2-18 困ったことは遠慮なく相談する
2-19 まずは一報を忘れず対応する
7 外部機関との連携を図る
2-20 どのような機関と連携するのかを把握する
2-21 児童・生徒の問題行動への対応で連携する
2-22 特別な支援を要する児童・生徒の支援で連携する
2-23 地域のサポーターと連携する
3章 学校を改善する
1 教職員の意識を変える
3-1 教職員の意識を改革する
3-2 やりがいを追求できる職場をつくる
2 分掌・分担を改善する
3-3 分掌のあり方を考える
3-4 人員不足を解消する
3 ICT機器を使う
3-5 教頭・副校長が使い方を理解する
3-6 ICT機器を指導に使う
3-7 ICT機器を業務に使う
4 授業研究を活性化する
3-8 全員が関わる授業研究にする
3-9 子どもの姿を語る協議会にする
3-10 協議会の指導・講評を改善する
4章 働き方を変える
1 教頭・副校長の業務を改善する
4-1 組織を活用する
4-2 教職員に仕事を任せ、進行管理は細かく行う
4-3 幹部職員と連携する
4-4 教頭・副校長の仕事を見直す
4-5 補助員等を活用する
2 教頭・副校長の仕事を工夫する
4-6 事務処理は一気に行い、事務処理をしない時間をつくる
4-7 処理が必要な文書は、色別に分類する
4-8 期限を守る
3 教頭・副校長の働き方を変える
4-9 QOLの向上を目指す
4-10 ON・OFFを区別する
4-11 授業を楽しむ
4-12 多くの本を読む
4-13 自分の得意な世界を充実させる
4 教育委員会との関わりを改善する
4-14 教育委員会を活用する
4-15 各種調査を業務改善につなげる
5 教員の働き方改革を進める
4-16 業務を見直し計画的に業務を薄める
4-17 ICT機器を活用する
5章 教員を育てる
1 計画的に人材を育成する
5-1 校内研究を通して人材を育成する
5-2 OJTを活用して中堅教員を育成する
5-3 長期休業を自己研鑽の機会として位置づける
2 ミドルリーダーを育てる
5-4 日常の授業観察を定期的に行い、よい点・改善点を伝える
5-5 分掌に特化した声かけを行う
5-6 他学級の児童・生徒の話題を話す
3 ミドルリーダーの指導力を向上させる
5-7 良好な成果の実施計画の改善点を2つ考えさせる
5-8 課題のある実施計画の改善点を3つ考えさせる
5-9 「報告・連絡・相談」を確実に行わせる
4 若手教員を育てる
5-10 前週中に週案の内容を確認する
5-11 文書による情報提供はマーカーを引いて渡す
5-12 毎日必ず報告させる
5 若手教員の指導力を向上させる
5-13 指導担当教員からの「報・連・相」を徹底する
5-14 若手教員を伸ばすための日常の授業観察をする
5-15 健康管理に配慮する
6 年配教員のやる気を引き出す
5-16 評価をふまえた声かけをする
5-17 解決すべき課題を提示する
5-18 若手教員を活用する
5-18 ベテランを活用して学校文化の継承と改善をする
7 教職員を指導する
5-19 全体にかかわる指導はゆっくりと確実に行う
5-20 個々の教員への指導は個別に行う
5-21 教員以外の学校職員を指導する
6章 子ども・保護者・地域と関わる
1 児童・生徒の状況をつかむ
6-1 家庭環境を把握し、適切に対応する
6-2 特別支援教育の推進を図る
6-3 児童・生徒と関わる
2 保護者とつながる
6-4 全体に向けた情報発信を工夫する
6-5 個別の情報発信に配慮する
6-6 保護者には、日常から挨拶と声かけをする
3 保護者・PTAとの関わりを改善する
6-7 PTAとの関わりを改善する
6-8 保護者との関わりを改善する
4 地域とつながる
6-9 学校行事で地域にアピールする
6-10 地域の方の家まで足を運び、要件を伝える
6-11 地域の力を活用する
6-12 教職員を地域の行事に積極的に参加させる
5 地域との関わりを改善する
6-13 地域学校共同本部を活用する
6-14 町会・自治会・商店会等との関わりを改善する
6-15 スポーツ団体・文化団体との関わりを改善する
おわりに