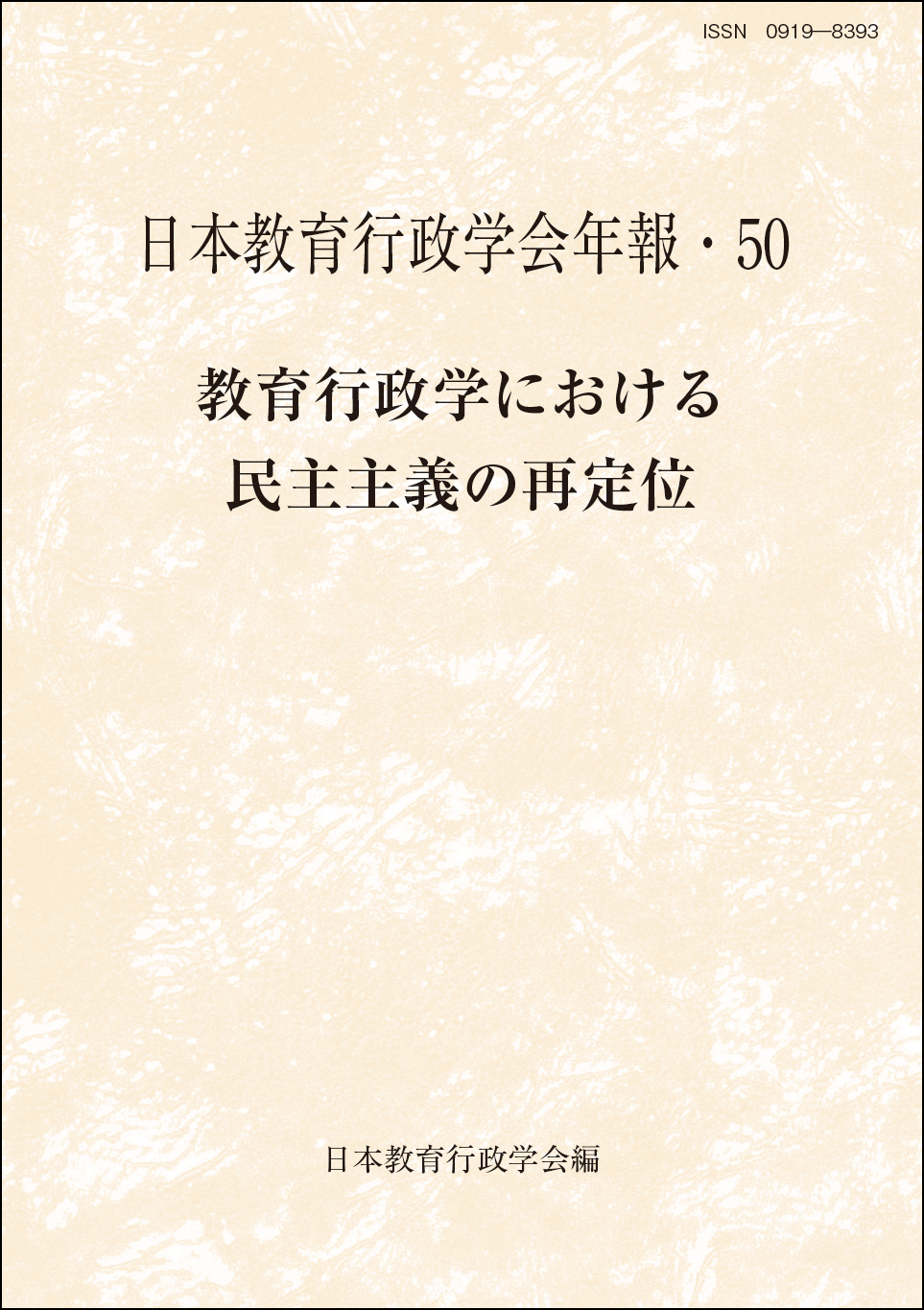日本教育行政学会年報No.50 教育行政学における民主主義の再定位
[本書の概要]
[編集] 日本教育行政学会
[刊行日] 2024-10-11 [形態] 書籍
[定価] 3740 円(税込) [判型] A5判 [頁数] 312頁
[ISBN] 978-4-86560-601-0
[本書の目次]
Ⅰ 年報フォーラム 教育行政学における民主主義の再定位
1.教育行政学と「民主主義」―戦後初期の宗像誠也を素材として―
2.現代学校制度における多様性・公正性・包摂性の位相
――学びの場を「分けること」の是非をめぐって―
3.教職における専門性の民主主義的再検討
――「リスク」への応答をめぐる試論―
4.アメリカにおける民主主義的な学校を実現する地方学区事務局の役割
――校長指導職の職務変容と専門職基準に着目して―
5.熟議デモクラシーにおける教育政策の正統性―相互性を中心に―
・【訂正】p.101に誤りがありました。正しくは以下の通りです。お詫びして訂正します。
・・※〈註・引用参照文献〉(28)の冒頭 Ibid.,p.97. を削除し、(31)の冒頭に Ibid.,p.97. を挿入する。
Ⅱ 研究報告
1.戦後日本の教育行政における「通級による指導」概念の変容
――1990年代以前の統合教育をめぐる文部省、中教審、臨教審の議論を手掛かりに―
2.公立不登校特例校の設置過程における教育委員会の主導性
――住民との合意形成を中心に―
3.米国シカゴの学校協議会にみる生徒参加の影響力と課題
――校内警察官配置の存廃をめぐる意思決定の事例から―
4.公立学校教員の懲戒処分に関する厳罰化傾向の検証
――59自治体の処分件数と処分量定の変化に着目して―
5.「広域分散型」自治体における公立通信制高校の機能と限界
――高校教育機会保障の視点から―
Ⅲ 大会報告
◆シンポジウム 公教育保障の外延を見極める
1.千葉市初の夜間中学校 真砂中学校かがやき分校
2.不登校政策は設置・配置主義からインパクト志向への転換を
――カタリバの現場から見えること―
3.公教育の外延拡張が意味するもの
――形式的平等・公正・ケイパビリティの観点から―
◆課題研究Ⅰ 教育行政の専門性・固有性の解体と変容(1)―官邸主導改革と教育行政
1.教育政策と中央教育行政の変容をどう捉えるか
2.権力の集中とその空洞化の中で進む既成事実への屈服
3.科学・学術研究と政府の関係はどう規律されるべきか
――「日本学術会議の在り方問題」を中心に―
◆課題研究Ⅱ 令和の日本型学校教育下における教師の職務の変容と教師をめぐる専門性の再定位
1.空洞化する教師の「専門家としての学び(professional leaning)」
――「令和の日本型学校教育」を担う教師の養成・採用・研修等の在り方について~「新たな教師の学びの姿」の実現と、
――多様な専門性を有する質の高い教職員集団の形成~(答申)(中教審第240号)において―
2.「学習化」する教育における教師の役割―教育方法学の視座から―
3.「令和の日本型学校教育」下の教員業務を展望する
◆若手ネットワーク企画
若手ニーズ調査からみる日本教育行政学会のゆくえ
Ⅳ 書評
1.葛西耕介〔著〕『学校運営と父母参加―対抗する《公共性》と学説の展開―』
2.髙野貴大〔著〕『現代アメリカ教員養成改革における社会正義と省察―教員レジデンシープログラムの展開に学ぶ―』
3.前田麦穂〔著〕『戦後日本の教員採用―試験はなぜ始まり普及したのか―』
4.大島隆太郎〔著〕『日本型学校システムの政治社会学―教員不足と教科書依存の制度補完性―』
5.滝沢潤〔著〕『カリフォルニア州における言語マイノリティ教育政策に関する研究
――多言語社会における教育統治とオールタナティブな教育理念の保障―』
6.前原健二〔著〕『現代ドイツの教育改革―学校制度改革と「教育の理念」の社会的正統性―』
7.青井拓司〔著〕『教育委員会事務局の組織・人事と教育行政プロパー人事システム
――地方教育行政における専門化と総合化の融合に向けて―』