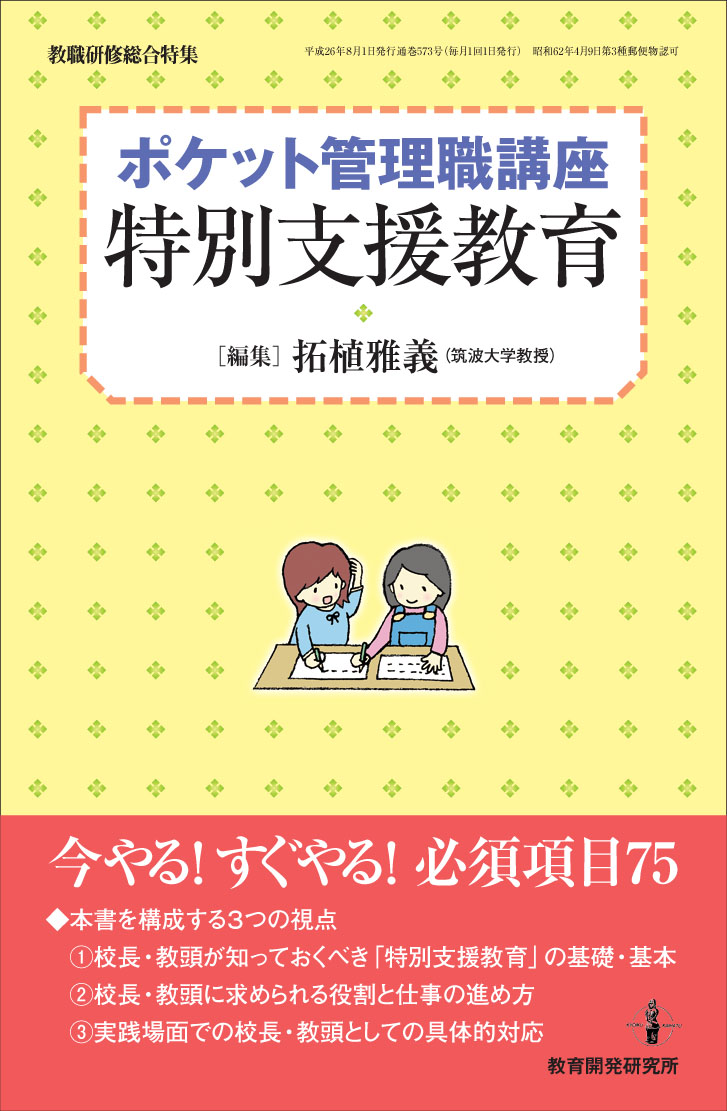ポケット管理職講座「特別支援教育」(今やる、すぐやる、必須項目75)
[本書の概要]
★「インクルーシブ教育って何? 校長・教頭は何をすればいいの?」「障害者差別解消法ってどんな法律? 学校にはどんな義務がある?」すべての疑問にピンポイントに答えます!
★小・中学校で特別支援教育についての体制整備・支援、教員への指導・助言、評価等を行う校長・教頭のためのハンディサイズのガイドブック遂に刊行!
★必要にして十分な知識を網羅! 管理職試験対策にも最適!
★本書を構成する3つの視点:①校長・教頭が知っておくべき「特別支援教育」の基礎・基本、②校長・教頭に求められる役割と仕事の進め方、③実践場面での校長・教頭としての具体的対応。
[編集] 柘植雅義
[刊行日] 2014-06-19 [形態] ムック
[定価] 2090 円(税込) [判型] B5判 [頁数] 192頁
[ISBN] 978-4-87380-671-6[雑誌コード] 63016-61
[本書の目次]
はじめに
■第1部■管理職が知っておくべき特別支援教育の基礎・基本
●特別支援教育
●教育的ニーズ
●発達障害への対応
●特別支援教育システムの構築
●PDCAサイクルによる推進
●教育基本法
●学校教育法
●学校教育法施行規則・施行令
●障害者基本法
●発達障害者支援法
●校内委員会(校内特別支援教育推進員会)
●特別支援教育コーディネーター
●個別の指導計画
●個別の教育支援計画
●特別支援学校のセンター的機能
●連携のポイント
●保護者との連携・保護者への支援
●教育機関との連携
●保健・福祉・労働機関との連携
●医療機関との連携
●インクルーシブ教育システム構築
●合理的配慮
●基礎的環境整備
●国連・障害者の権利に関する条約
●障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律
■第2部■管理職の役割と仕事の進め方を理解しよう
●特別支援教育推進のリーダーとしての心構え
●校内特別支援教育推進の基本方針の明確化
●学校経営計画への特別支援教育関連事項の記述
●特別支援教育推進年間計画の作成
●学校評価への特別支援教育にかかわる項目の設定
●教職員の意識改革
●校内システム改革
●PDCAサイクルによる推進の留意点
●教職員の校務分掌割り当て
●特別支援教育に係る経費・財務
●特別支援教育コーディネーターの指名
●校内における特別支援教育推進の委員会の設置
●特別な配慮の必要な児童・生徒の実態把握
●特別支援教育に係る教育課程の作成
●個別の指導計画・個別の教育支援計画の作成
●通常の学級担任に求められる専門性
●通級による指導・特別支援学級における指導に係る専門性
●校内研修会の進め方
●市町村や都道府県における研修の進め方
●地元の大学・大学院や国立特別支援教育総合研究所への現職派遣研修
●学校風土の醸成
●保護者との連携
●地域住民の理解と協力体制
●民生委員・児童委員らとの連携
●開かれた学校づくり
■第3部■実践場面で考える管理職としての具体的対応
●特別支援教育コーディネーターを指名する際の配慮点は何か?
●特別支援教育コーディネーターを管理職としてどのように支えるか?
●校内特別支援教育委員会をいかに機能化させるか?
●校内研究で取りあげたいテーマは?
●校内研究の推進の工夫点は?
●なぜ早く「気づく」ことが重要か?
●「気がつかなかった」ということのないようにするための工夫は?
●学習のつまずきを改善していくためには?
●障害のあることで、いじめにならないような工夫は?
●障害があることで不登校にならないようにするための工夫は?
●授業の基本的な考えをどのように教職員に伝えていくか?
●ユニバーサルデザインを学校としてどのように推進するか?
●授業がうまく進められない教員にどのような支援をするか?
●校内の授業研究会をどのように工夫すればよいか?
●保護者向け授業参観の工夫点・配慮点は?
●特別支援教育の重要性をいかに教職員に伝えていくか?
●通級による指導や特別支援学級の担当教師の専門性向上をいかに支えていく
か?
●通常学級の担当教員の専門性向上をいかに支えていくか?
●校内研修会をいかに企画したらよいか?
●校内研修会で、外部講師を招聘する際の配慮事項は?
●学校としての基本的な姿勢は?
●特別支援教育についてほとんど知らない保護者との連携と支援は?
●特別支援教育についてとくに詳しい保護者との連携と支援は?
●保護者から子育ての仕方など個別の相談を受けた際への対応の工夫点は?
●PTA総会・定例会で特別支援教育を取りあげる際の工夫点は?