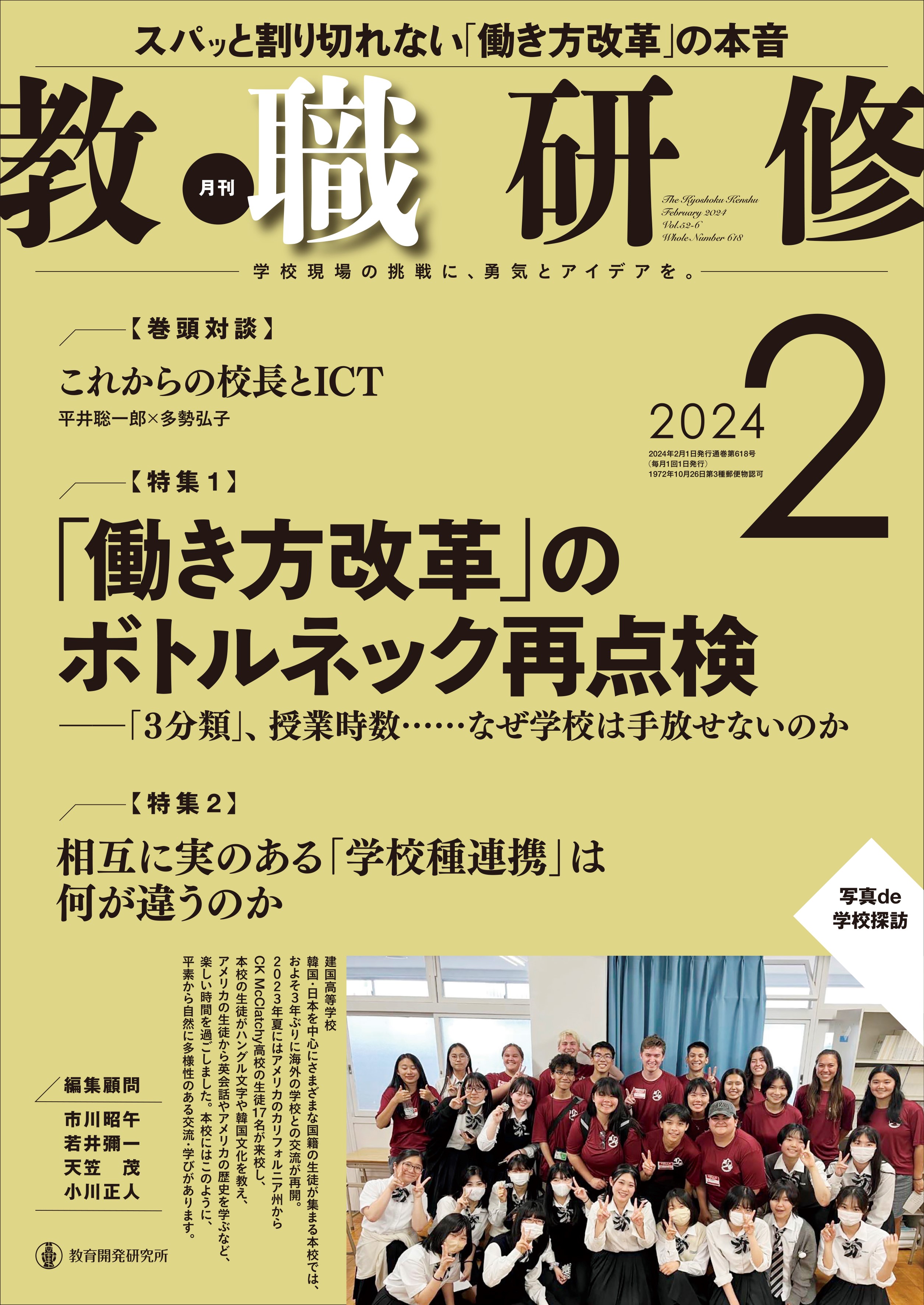教職研修2024年2月号〈特集:「働き方改革」のボトルネック再点検 「3分類」、授業時数 なぜ学校は手放せないのか/相互に実のある「学校種連携」は何が違うのか〉
[本書の概要]【定期購読のお申込】
特集1
「働き方改革」のボトルネック再点検 「3分類」、授業時数 なぜ学校は手放せないのか
「質の高い教師確保部会」緊急提言(2023年8月)で、働き方改革に向けて教員の業務の整理があまり進んでいないことが明らかになりました。学校現場からは「働き方改革はやり尽くした」との声もありますが、他校では手放せているのに自校では手放せていない業務があり、現時点で「やりつくした」と見直しを終えてしまっては現状は変わりません。本特集では、業務を手放せている事例等を紹介しながら、簡単に業務を手放させない学校現場の事情に寄り添いつつ、そのなかでも働き方改革を進めている事例等を紹介しながらどうすれば手放せるのか、を考えます。
特集2
相互に実のある「学校種連携」は何が違うのか
保育所・幼稚園から小学校、小学校から中学校と進む子どもたちが乗り越えていく課題は多く、そのとき子どもたちがつまずいても前に進めるように、側で教師が支えていける学校種間の連携の大切さが学習指導要領でも掲げられています。しかしながら、実際には、最低限の申し送りや形式的な交流、一部の担当者任せ、理解不足で連携先に不満等、学校種間での連携が上手くいっていない現状があるようです。そういった現状を踏まえ、管理職のかかわりを見つめ直しつつ、全教職員がもっと充実させてみようと思える"相互に実のある"学校種間連携を探ります。
[監修] 市川昭午/若井彌一/天笠茂/小川正人
[刊行日] 2024-01-19 [形態] 月刊誌
[定価] 1200 円(税込) [判型] B5判 [頁数] 140頁
[雑誌コード] 03059-02
[本書の目次]
巻頭対談
これからの校長とICT
平井聡一郎/多勢弘子
特集1
「働き方改革」のボトルネック再点検
――「3分類」、授業時数……なぜ学校は手放せないのか
-
【読者アンケート①】「3分類」の業務、手放せていますか? ◆ アンケート①
【インタビュー】松本市立波田小学校の「働き方改革」で大切にしたことは――「登下校対応」を「手放す」とすることへの違和感 ◆ 三輪千子/荒井英治郎
標準授業時数をどう考えればよいのか ◆ 冨士原紀絵
保護者の理解をどう得るか ◆ 森万喜子
学校現場で自分たちで変える――3分類表を活用したワークショップ ◆ 大野大輔
【読者アンケート②】教育委員会に言いたい! この業務はもうやめてほしい ◆ アンケート②
行政の権限と責任で進めなければならないこと ◆ 櫻井直輝
学校の「業務」を考える――「日本型学校教育」を問い直す◆ 広田照幸
特集2
相互に実のある「学校種連携」は何が違うのか
-
手間以上の価値がある学校種連携――幼・保・小の架け橋はどう役立つ ◆ 無藤 隆
接続時の子どもの「心」を支える環境の整え方 ◆ 外山美樹
新しい連携のかたちがコロナ禍で生まれた ◆ 朝倉 淳
学校種間の「段差の意義」を踏まえた連携のあり方 ◆ 大島充代
好評連載
学校マネジメント・学校経営
-
みんなの「権利」を大切にする学校 “縦ベクトル”の権利行使 ◆ 真下麻里子
「令和の日本型学校教育」が問う学校経営 学校裁量による自主的・自律的マネジメント(その5)――“チーム学校”と学級担任 ◆ 天笠 茂
OODAループで学校改善12ヵ月 地域との連携 ◆ 喜名朝博
フキゲンな職員室の労働安全衛生を見直そう。 本人の居ないところで本人の話をしない ◆ 大石 智
妹尾さんに聞きたい!学校お悩み相談室 休憩時間が授業や給食にかぶってて、とれません ◆ 妹尾昌俊
今月の学校経営 ◆ 栗田嘉也/鶴見悦子
校長のネットワーク力 ドラえもんのポケット ◆ 熊谷恵子
学校づくりのスパイス――異分野の知に学べ なぜ間違いが大切なのか ◆ 武井敦史
子どもを支える武器になる! 令和の「特別支援教育の視点」 学校の役割 ◆ 大西孝志
教育課程
-
こども学習指導要領 学校段階間の接続ってなに? ◆ 秋田喜代美
生涯エージェンシー宣言!「自己実現」と「社会」の切り離せない関係 エージェンシーを育む教育課程④すべてを結びつけ、子どもたちと協創 ◆ 木村 優
ひらかれた授業をつくる 小田原の教育をひらく ◆ 栁下正祐
教育×デジタル新潮流 AI時代の到来で転換点にあるプログラミング教育――小・中・高の段階的なレベルアップと創造的なプログラミングの重要性 ◆ 讃井康智
管理職の資質・職務
-
みんなに伝えたい「ことば」 学校のなかの「ふつう」を捨てませんか ◆ 木村泰子
私の学校経営信条 面白い!から学びがはじまる~Super Creative High Schoolを目指して~ ◆ 福田 崇
教頭の挑戦 問題解決の過程をともに経験する ◆ 小川 晋
この「失敗」が私を成長させた 何を言うかでなく、誰が言うか ◆ 宇田陽一
これからの校長の資質・能力 これからの校長の選考のあり方 ◆ 川上泰彦
「声かけ」で学校を動かす!北石原校長の12ヵ月 年度末の学校行事をどうするか ◆ 渡辺秀貴
副校長・教頭を楽しむ 「アイデア」を楽しむ ◆ 奥 雅美
児童・生徒
-
コロナ禍の子どもたち 子どもの摂食症とその予防 ◆ 北島 翼
不登校の論点 「子どもたちはどうして学校に来るのか」から考える学校づくり ◆ 町田実徳
教育時事
-
教育の断面 自分より優秀な生徒をどう扱うか ◆ 冷泉彰彦
新・教育直言 全部つながっている ◆ 浅田和伸
教育ニュースPick up ◆ 深津 誠
教育備忘録
〈深掘り・先読み〉教育ニュース 次期学習指導要領の改訂論議が本格化へ ◆ 渡辺敦司
フィンランド見聞録――幸せの国の学校現場から 「フィンランド教育に失望」? ◆ 徳留 宏紀
データ駆動型社会における「人間」と「教育」 生成AIの台頭が突きつけた問い――教育を捉える前提の揺らぎ ◆ 間篠剛留
宗教2世への対応、こんなときどうする?
①法解釈の観点から ◆ 鈴木秀洋
②先生の一言で救われる――支援機関との連携を ◆ 秋本弘毅
③子どもの人権・その先の幸せを守る――伴走型支援団体から ◆ 夏野なな
教育法規
-
スクールロイヤーと考える学校経営 地域学校協働本部の法律問題 ◆ 神内 聡
法律で読み解く学校経営プロブレム 総合的な学習の時間の意義と充実を考える――体験活動とその危機管理 ◆ 坂田 仰
教育行政・施策
-
行政職員日記 大人の島留学にかかわり学んだこと ◆ 豊田庄吾
地方から始まる学びの変革 地域連携による持続可能な学校部活動 ◆ 遠藤洋路
講座 教育行政入門 地方自治体の教育行財政―仕組みと運⑲都道府県と市町村の教育行財政関係(14) ◆ 小川正人
学校総論――改めて学校とは何か 私立学校の基本的性格 ◆ 市川昭午
コラム
-
七転八起 次世代管理職 一人ひとりの中に宝を見つける ◆ 屋良真弓
やわらかキョウイクアタマ インクルーシブ教育は、ノリが悪いんです…… ◆ 赤木和重
気になる!教育関連用語解説 OD / オーバードーズ ◆ 古藤吾郎
@教育相談室――子どもの「今」「これから」に寄り添った支援 普通にどうでもいい会話がしたい――信仰を持つ家庭の子どもの声 ◆ 坂下たま子
きょういくパノラマ 子どもの見ている景色
教職いろはがるた スキナーの行動分析学を学んでいこう! ◆ 三田地真実
ブックレビュー&ガイド
宿しておきたい親子・先生のはなし できない人から見ると、できる先生は不思議な人 ◆ 富田富士也
校長会・教頭会 事務局の中から ◆ 小泉与吉/宮本久也
教職研修フォーラム
保護者レンズを通してみると ◆ 前田裕子/パウロタスク
管理職選考突破!講座
-
管理職選考 合格への道 論文試験のねらいと書き方 ◆ 榅山範夫
速報!管理職選考問題 ( 岩手県/千葉県/千葉市/富山県/滋賀県 )
頻出教育調査の傾向 国際学力調査②TIMSS ◆ 後藤武俊
最新告示・通達の提要 「『教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策(提言)』を踏まえた取組の徹底等について(通知)」2023年9月8日 ◆ 植竹 丘
実践演習! 論文添削講座 ◆ 嶋田 優/江口恵子