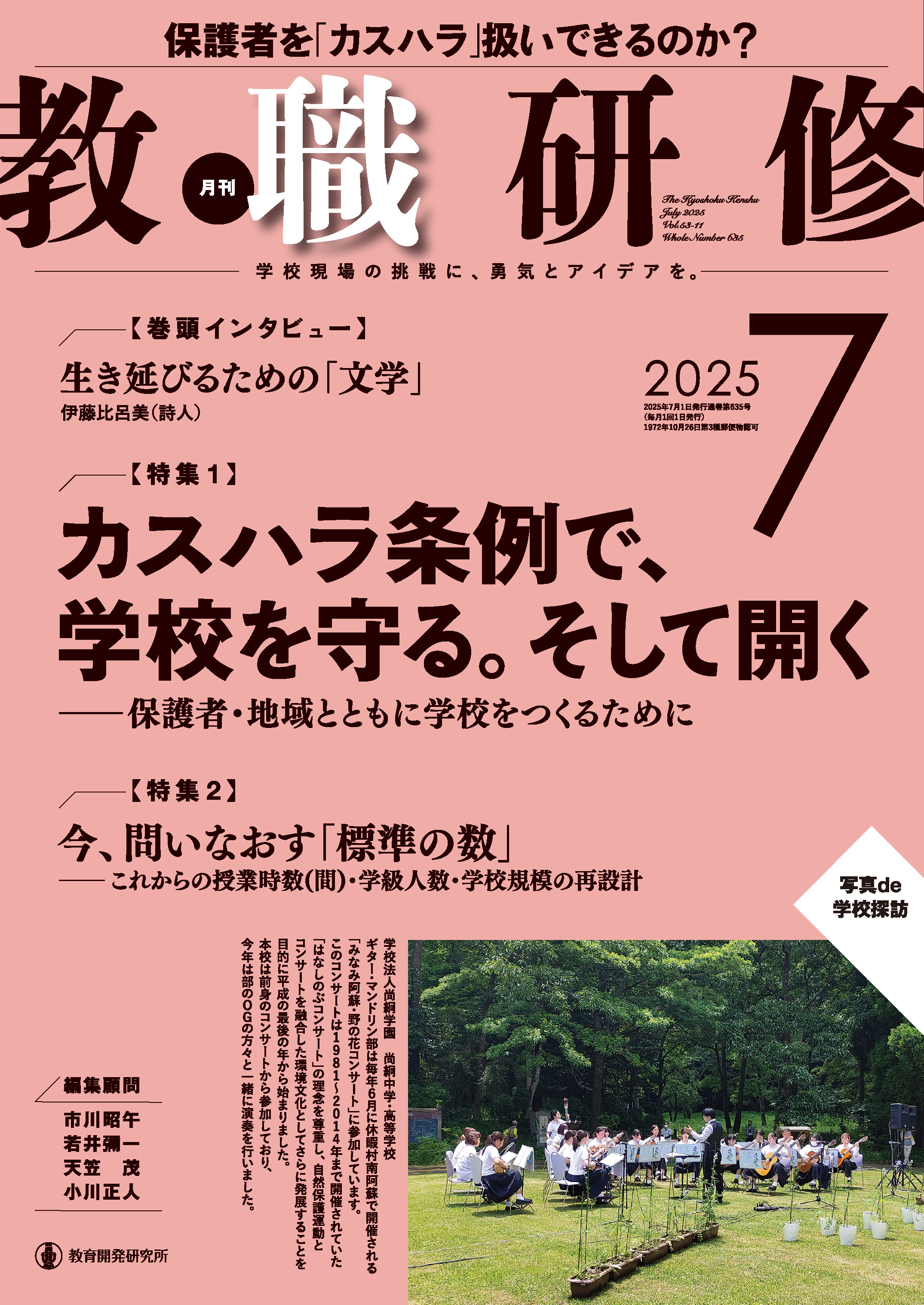教職研修2025年7月号〈特集:カスハラ条例で、学校を守る。そして開く /今、問いなおす「標準の数」〉
[本書の概要]【定期購読のお申込】
特集1
カスハラ条例で、学校を守る。そして開く――保護者・地域とともに学校をつくるために
- 2024年、東京都の「カスタマー・ハラスメント防止条例」(カスハラ条例)が成立し、12月に「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」が公表されました。各地で同様の条例が成立し、今後全国に広がることが予想されます。東京都のカスハラ条例・ガイドラインでは、顧客からの就業者に対する「カスハラの禁止」を明示し、学校も「就業者」に含まれています。一部の保護者対応で学校が疲弊するなか、ガイドラインのもとで学校が守られることを期待してもよいのでしょうか。他方で学校が「耳が痛い」ことをすべて「カスハラだ」と受けとめては、よりよい学校づくりにつながりません。管理職として「カスハラ条例」をどう受けとめればよいか、探ります。
特集2
今、問いなおす「標準の数」――これからの授業時数(間)・学級人数・学校規模の再設計
- 授業時数(間)、学級人数、学校規模――こうした「標準の数」は、公立学校が全国で等しく学びを保障するために設けられてきました。ですが今日、少子化、教員不足や働き方改革、1人1台端末の整備や個別最適な学びの広がりなど、教育を取り巻く環境が変化するなかで、現場とのズレが生じつつあります。次期学習指導要領に向けた審議が始まった今、新しい学びのかたちとともに、「標準の数」の意味とこれからを問いなおします。
[監修] 市川昭午/若井彌一/天笠茂/小川正人
[刊行日] 2025-06-19 [形態] 月刊誌
[定価] 1280 円(税込) [判型] B5判 [頁数] 140頁
[雑誌コード] 03059-07
[本書の目次]
巻頭
生き延びるための「文学」
伊藤比呂美(詩人)
特集1
カスハラ条例で、学校を守る。そして開く――保護者・地域とともに学校をつくるために
-
東京都「カスタマー・ハラスメント防止条例」を学校でいかす ◆ 内藤 忍
学校で何がカスハラにあたるのか ◆ 師子角允彬
【ケーススタディ】「カスハラ」があった場合の学校の対応 ◆ 岩崎孝太郎
「カスハラ」と学校管理職 ◆ 奥 雅美/伏見 滋
【座談会】学校は保護者に「カスハラです」と言えるのか? ◆ 新保元康/林 真未/大塚玲子
「正当なクレーム」の受けとめ方 ◆ 遠藤洋路
「専門性の尊重」が「ハラスメント」を遠ざける ◆ 真下麻里子
特集2
今、問いなおす「標準の数」――これからの授業時数(間)・学級人数・学校規模の再設計
-
その「標準の数」、何のためにある?――公立学校の使命とともに考える ◆ 天笠 茂
授業の「時数(間)」をもっと柔らかく設計する ◆ 冨士原紀絵
「35人学級」で本当に子どもは支えられているか-人数以外の要素もふまえた学級経営のこれから ◆ 藤井宣彰
効率や資源で語りきれない「学校規模」を探る道 ◆ 葉養正明
好評連載
学校づくり
-
世界の職員室から ホンジュラス編「学び合う教員へ」 ◆ 鈴木 萌
「令和の日本型学校教育」が問う学校経営 チームによる学級担任制(3)――小中一貫教育にとっての教科担任制 ◆ 天笠 茂
妹尾さんに聞きたい!学校お悩み相談室 議論できない職員室 ◆ 妹尾昌俊
今月の学校経営(配慮事項) ◆ 山田保彦
今月の学校経営(学校講話) ◆ 西田裕子
私たちの働き方改革 働きやすさ+働きがい ◆ 松野千恵美
【日本教育経営学会連載講座】学校改善ツール 国研「学びの環境」アセスメントツールモデル ◆ 宮古紀宏
「声かけ」で学校を動かす!北石原校長の12ヵ月 子どもに暴言!①組織としてどう対応? ◆ 渡辺秀貴
副校長・教頭の学校づくり羅針盤――笑顔でGO! 「人材育成」「人財育成」 その2中堅・ベテランの指導 ◆ 矢野 渡
学校づくりのスパイス――異分野の知に学べ 去りゆく者の特権 ◆ 武井敦史
学校DE&I――多様性を受けとめる場をめざして 学び方の「ふつう」もいろいろ ◆ 武田 緑
管理職のすがた
-
みんなに伝えたい「ことば」 「困る子」をつくらない ◆ 木村泰子
私の学校経営信条 Your dream is our dream. Our dream is Narikoku’s dream!~皆さんの夢実現に全力を尽くします~ ◆ 福水勝利
教頭のまなざし 機略縦横にやればできるを背中で示す ◆ 杉山一郎
学校経営の道具としての概念化スキル入門 「概念化スキル」をどう鍛錬するか――具体例 ◆ 諏訪英広
この「失敗」が私を成長させた 自他すべての失敗から学ぶ ◆ 藤本泰雄
教頭ピボット!――5年後の管理職へ贈る 奮闘と成長のマイルストーン記録 校長を知り教頭を知る ◆ 杉本敬之
教育行政
-
行政職員日記 「通訳できる存在でいたい」。 ◆ 小泉志信
地方から始まる学びの変革 働き方改革から授業改善の流れを作る ◆ 福本 靖
講座 教育行政入門 学校教育費負担軽減の取り組み(2) ◆ 小川正人
教育課程
-
子どもも教師も自ら学び、動きだ出す! 特活2.0 生きる力に向かって、鍛える資質は二つだけ ◆ 清水弘美
授業研究で学校をつくる――教師の同僚性をみがく 対話的に語りあう場をつくる ◆ 小林宏己
新しい教育、どうなった? 道徳科を本当の教科にするために次期学習指導要領ができること ◆ 柳沼良太
深掘り・先読み〈教育課程改革〉 中学校技術を別教科に、「総合探究」と連携へ ◆ 渡辺敦司
教育×デジタル新潮流 私たちはケータイやスマホとどう接するべきなのか――使い方次第論と規制論の狭間で① ◆ 石田光規
特別企画:学習指導要領改訂「諮問」アンケート 学習指導要領「改訂諮問」アンケート
子どもたちの今
-
子どもと社会の現在地 16PersonalitiesとMBTI(R) ◆ 小塩真司
不登校の論点 不登校当事者の実態とニーズを把握し、官民共創でつくる効果的な施策とは?下 ◆ 鈴井孝史
増え続ける発達障害とどう向き合うか 発達障害の理解を進めるための教職員研修とは ◆ 堤 英俊
@教育相談室――子どもの「今」「これから」に寄り添った支援 体格で役割を押しつけられること ◆ 坂下たま子
教育時事
-
教育の断面 高校授業料無償化 置き去りにされた高校教育の将来像 ◆ 氏岡真弓
新・教育直言 「他流試合」で力を試してみよう ◆ 浅田和伸
教育ニュースPick up ◆ 斎藤文太郎
気になる!教育関連用語解説 SEL ◆ 下向依梨
データ駆動型社会における「人間」と「教育」 先端技術との関係を問う――障害と技術の結びつきから ◆ 宮本 聡
教育法規
-
法律で読み解く学校経営プロブレム 学校配付物の事前チェック――管理職の重要な職務 ◆ 坂田 仰
〈検証〉12年目のいじめ防止法 学校の「いじめの重大事態」への対応の問題 ◆ 伊藤美奈子
コラム
-
七転八起 中堅教員 同志とともに学び続ける教師でありたい ◆ 深井正道
続・やわらかキョウイクアタマ プー横丁の横丁って、どんなとこ? ◆ 南浦涼介
きょういくパノラマ 教員の働き方改革のゴールとは? ◆ 匿名
♯若手の困りごと 4月のドタバタ ◆ 匿名
税所一家のシュタイナーをめぐる冒険 シュタイナー教育ってなんなんだろう!? ◆ 税所篤快
校長会・教頭会 事務局の中から ◆ 小泉与吉/冨士道正尋/井部良一
校長・教頭のセカンド★キャリア キャリアコンサルタント ◆ 工忠憲正
市川昭午の往古来今 昔の生徒と学生 ◆ 市川昭午
ブックレビュー 学びの本質 ◆ 浜野 隆
ブックガイド ◆ 福原英信
保護者レンズを通してみると ◆ 前田裕子/パウロタスク
管理職選考突破!講座
-
管理職選考 合格への道 面接試験のねらいと受け答え方 ◆ 横畠道彦
速報!管理職選考問題 ◆ 面接問題①
頻出法規・客観問題の演習 会計年度任用職員に関する客観問題 ◆ 原北祥悟
頻出教育調査の傾向 生徒指導上の諸課題に関する調査 ①いじめ ◆ 江上直樹
最新告示・通達の提要 「教職員等の選挙運動の禁止等について(通知)」2024年10月10日 ◆ 小林昇光
頻出面接問題の演習 多忙解消に関する面接問題 ◆ 奥山 勉
実践演習! 論文添削講座 ◆ 矢島 正/江口恵子